静岡市 小児科・アレルギー科(予防接種・乳児健診) 静岡市駿河区中田

054-285-3821
静岡市駿河区中田2-3-17
特集
子どもにとっての遊び
ここ数十年で日本人の子どもの遊びの文化が変化してきました。昔は男の子はめんこやチャンバラ遊び,女の子はゴム跳びやままごと遊びなどよく見かける事が多かったですが,今は家でゲーム遊びという時代になってしまいました。安全に遊ぶ所も少なくなっており,仕方のない面もあるのかもしれません。遊びは体を動かしたり他人との関わりやルールを学び社会性を身につけます。ゲームやテレビは一方通行で社会性やコミュニケーション能力を養うことはできません。ゲームは自分本意になってしまうので相手の気持ちを読み取る能力は養えません。また,思春期や大人になってからもコミュニケーションがとれなかったり,人との接し方が不得意になったりします。3月は暖かい日もあると思いますので,休みの日は親御さんも外遊びにつきあったり,一緒に体を動かしてみましょう。また,「いつも遊んでないで勉強しなさい!」なんて言っていませんか?「たまには外でしっかり遊んできたら?」と声をかけてあげて下さい。きっと楽しく遊んだ後は子どものとびっきりの笑顔が見れると思いますよ。

特集
こどもの寝かしつけ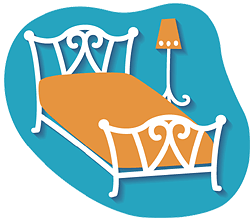
子どもの寝かしつけ。
どのご家庭でも悩まれていることではないでしょうか?
日中、子供がどのようにして過ごすのかが「夜の良い眠り」と深く関わってきます。
朝は太陽の光を浴びさせる
朝は子供が眠っている部屋のカーテンを開け、太陽の光を浴びさせましょう。人間は太陽光のような「強い光」が目に入ってくると、メラトニン(眠りを誘うホルモン)の分泌を抑え、私たちは気持ちよく目覚めることができます。また、メラトニンの分泌を抑えてから、約14時間でまたメラトニンの分泌を始めます。そうすると、人間は「眠気」を感じ、心地よく眠りにつくことができるのです。
日中はしっかり遊ばせる(運動させる)
眠りにつくためには、「程よい肉体的な疲労」も大切です。日中はしっかりと身体を動かせ、たくさん遊ばせるようにしましょう。
長時間のお昼寝は午後3時まで
「長時間の昼寝は午後3時までに終わらせる」というのを目標にしましょう。
眠る前は「強い光」を見させないようにする
眠る前に強い光を見てしまうと、メラトニンの分泌を抑えてしまいます。子供が眠る2時間前からは、強い光を放つテレビ・スマホ・パソコン・ゲームなどの画面を見せないようにしましょう。子供を寝かしつける際は、お部屋の照明を薄暗くしましょう。
眠前にする行動をルーティン化する
夜にすることは、毎日同じ流れでするのがおすすめです。お風呂のあとは歯磨き!など、『〇〇の次は、××』が決まっていると、子どもは安心します。そして、寝る前の儀式が決まっていると、寝かしつけも楽になります。
特集
嘔吐物処理、正しくできていますか??
吐物処理の際に処理を行う人が感染してしまう可能性や感染を広げる媒介者になってしまう危険があります。マスク、エプロン、手袋を適切に使用し、自分が感染したり感染源を体に付着させ広げてしまったりすることがないようにしましょう。吐物処理の際には、できるだけ使い捨てできる物品を使用しましょう
必要物品
ペーパータオルや使い捨ての布、ペットシーツ等 ・使い捨て手袋2組 ・ビニール袋2枚 ・使い捨てマスク ・消毒薬
消毒薬の作成方法
家庭用漂白剤(ハイター等)10ml(ペットボトルキャップ2杯分)+水500mlで0.1%の消毒液が完成!
片づけ方法
吐物は広範囲に飛び散ります。吐物を中心に周辺2mの範囲を外側から吐物に向かって拭く。目に見える吐物を外側から内側に向けて消毒液に浸したペーパータオル等で静かに拭き取り、1枚目のビニール袋に捨てる。この時、1枚目の手袋も捨てます。
注意!同じ拭き取り面を繰り返し使用しない(感染が拡大するため)
拭き掃除は一方向が基本です。
新しい手袋に変え、吐物があった所に消毒薬を浸したペーパータオルを広げて放置(10分程度)
ペーパータオルを回収、破棄した後、床に残った消毒液を拭き取るため水拭きする。
装着していた手袋、マスク、等不潔な部分に触れないよう脱ぎ2枚目のビニール袋に破棄する。
気が付かないうちに手が汚れているかもしれません。吐物処理を終えた後は必ず手を洗いましょう。


特集
鼻のかみ方
小さな子どもに、鼻のかみ方を教えるのは意外と難しいものです。「鼻水ぐらい」と、気楽にかまえて放っておくと、中耳炎や副鼻腔炎など、新たな病気を引き起こすこともあります。遊びを取り入れながら、鼻のかみ方を上手に教えてあげましょう。
子どもに、鼻のかみ方を教えようとしても、なかなかうまくいかないですね。「お鼻、フンして」と言うと、口で『フン』と言う・・・。説明が、なかなか難しいですね。
通常、鼻の中の粘膜は適度に湿っているが、ウイルスや細菌が侵入してくると、それを流し出そうと鼻水の分泌が過剰になり、最初は透明でサラサラとしているが、粘膜の炎症が強くなってくると、青みや黄色みのある鼻水が出始めます。
①ティッシュを用意します。
②ティッシュを、短冊のように、細長く切りましょう。
③口から息を吸い、口をしっかり閉じます。
④片方の鼻の穴を指で押さえます。
⑤もう片方の鼻の穴から「フン」と、鼻息を出します。
―――→ その時、②で作ったティッシュを、上から持ってあげ、ティッシュが揺れるように。
機嫌も悪いので やめましょう.
まずは、お風呂でやってみましょう。
お風呂の中は、湿気が多く、鼻水がやわらかくなっていて出しやすいです。
お風呂で、お母さんがお手本を見せながら一緒にやってみましょう!

特集
乳児に蜂蜜は いつからあげていいのか
乳児に蜂蜜を与えてしまい、ボツリヌス菌により死亡してしまった悲しいニュースがありました。では、1歳になれば、与えて良いのか否かと考えると、その保証もないことに気がつきました。
国立感染症研究所に資料によると・・・
蜂蜜中にボツリヌス菌の胞子(芽胞)が含まれているおそれがあるので、蜂蜜は1歳未満の乳児に与えない。 乳児ボツリヌス症は、2~4カ月の乳児に最も多く、報告では、生後2ヶ月からや8ヶ月までの小児です。
日本製の蜂蜜は、ボツリヌス菌に汚染している確率は5%と言われます。
アメリカでは、蜂蜜の報告は少なく、コーンシロップ、水飴、砂糖など、完全に殺菌が施されていない天然甘味料からのボツリヌス菌の感染が多いようです。
しかし、上白糖や三温糖は、精製糖製造過程では紫外線により殺菌しているので、ボツリヌス菌が含まれているおそれはないそうです。
蜂蜜はいつからあげて良いかは、今まで言われていたように1歳でよいのではないかと思われます。
特集
早寝・早起き・朝ごはん 
生活習慣の改善には、『早寝早起き朝ごはん』が重要です。
心も体も健康的な生活を送るため、自分の生活を見直してみましょう。
![]() 早寝早起き:朝日をたっぷり浴びて、生体時計をリセットしましょう。
早寝早起き:朝日をたっぷり浴びて、生体時計をリセットしましょう。
早起きが習慣になれば、夜も早めに眠れるようになります。
授業中に眠くなるのは生活の乱れから! 
小中学生に「3、4時間目に眠くなりますか」と聞いたところ、小学生の5~6割、中学生では7~8割が眠くなると答えています。3~4時間目というのは午前10時~12時頃で、本来ヒトという動物が一番、目覚めていなければいけない時間帯です。この結果は子どもたちの多くが生体リズムを乱していると判断できます。
「寝ると太る」はウソ!
夜ふかしは慢性の時差ぼけとなり、体調不良になって、その結果、日中に十分活動できなくなり、運動量が低下して肥満になるのではないかと考えられます。もちろん、いったん太ってしまうと、そのために運動量が減り、ますます太る方向にすすみ悪循環です。多くの人は「寝ると太る」と思い込んでいるのではないでしょうか。ソファーに横になってスナック菓子を食べながらテレビを見ているような姿を思い浮かべるのでしょうが、これは寝ているのではありません。単なる運動不足です。
![]() バランスのよい食事:
バランスのよい食事:
朝ごはんを食べることは、心にも体にもとても大事なことです。
朝ごはんをしっかりと食べることによって、体を目覚めさせ、
脳のはたらきを活発にし、授業にも集中できます。
朝食をとらないとキレやすい?
朝食を食べない子はイライラのある子が、かなり多くなります。
こんな症状がでやすいです
・イライラする ・風邪をひきやすい
・頭が痛くなりやすい ・心配ごとがある
・だるくなりやすい ・元気が出ない
・夜よく眠れない ・ご飯がおいしくない
 こんなことをしていませんか?
こんなことをしていませんか?
・子どもが寝ているのに、家族がそばでテレビを見ている
大人はテレビを楽しんでいるのに、子どもだけ早寝させようというのでは、子どもだけが無理を強いられることになります。子どもが寝る時間になったらテレビを消すことを家族の習慣にしましょう。
・深夜に帰った家族ともコミュニケーションをとるようにしている
大人の時間に子どもの生活を合わせてはいけません。仕事などで、帰りが遅く、子どもとコミュニケーションがとれないのであれば、朝早く起きてふれあいの時間をもつようにしましょう
・起きるのが遅くて朝食がとれないので、夜食をたっぷりとっている
寝る前に夜食をとると、眠りが浅くなって生体リズムの乱れにつながり、朝に食欲がわかず、朝食抜きにつながります。
・朝は栄養バランスを考えて機能性食品で済ませている
食事は栄養をとることだけが目的ではありません。よくかむことで脳の血流や機能を活発にしたり、味や会話を楽しむことで、心の豊かさを育てたりと、様々な役割があるのです。
・家族の起きる時間がバラバラなので、一人ずつ食事をしている
子どもが一人で食べる場合は、好きなものばかりを食べてしまいがちになり、栄養がかたよってしまいます。一人ずつでの食事はできるだけ避けたいものです。
参考文献:今すぐ始めよう!早起き早寝朝ごはん
女子栄養大学 副学長 香川靖雄
東京ベイ・浦安市川医療センター長 神山 潤 共著
 054-285-3821
054-285-3821
